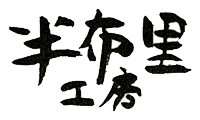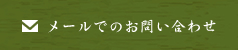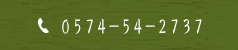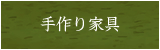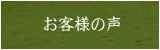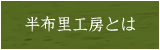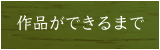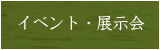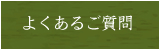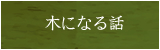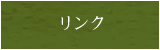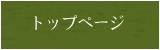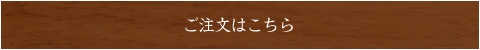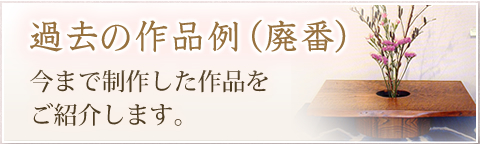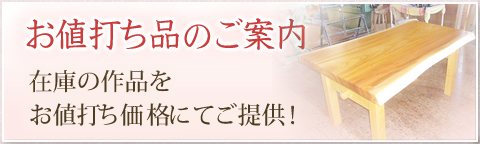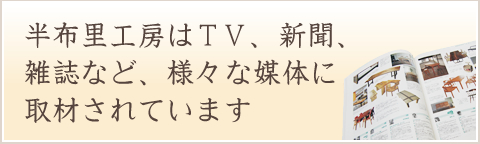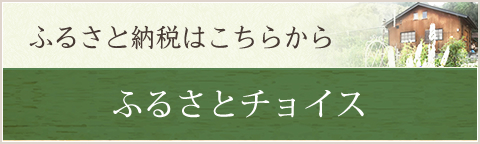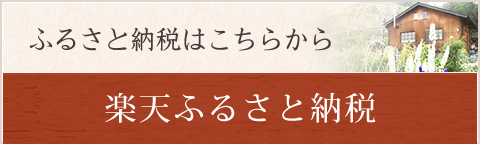- トップページ
- 里山便り2025
「猛暑の中でも…」
2025.09.02
 「幻」という意味は、日本ではもうほとんど入手が不可能ということです。2010年頃に絶滅危惧種のシベリアタイガーを保護する目的でロシアの法律が出来て、ベニマツを伐採することが禁止になり、輸出もしなくなったためです。
「幻」という意味は、日本ではもうほとんど入手が不可能ということです。2010年頃に絶滅危惧種のシベリアタイガーを保護する目的でロシアの法律が出来て、ベニマツを伐採することが禁止になり、輸出もしなくなったためです。たまたま当工房にはそれ以前に買ってあったものがあるので、それを使って制作できているということです。
 シベリア産ベニマツはとても素晴らしい材で、木目が緻密で節もほとんどなく、さらに松にありがちなヤニも出ません。(正確に言うとヤニツボというのがあって、その部分からしかヤニは出ないので、そういうところをカットして使えばいいのです。)
シベリア産ベニマツはとても素晴らしい材で、木目が緻密で節もほとんどなく、さらに松にありがちなヤニも出ません。(正確に言うとヤニツボというのがあって、その部分からしかヤニは出ないので、そういうところをカットして使えばいいのです。)経年変化で飴色に変わって、いい味になります。削ったときに出る甘くかぐわしい香りは、制作者しか味わえないものです。

 針葉樹は柔らかくて広葉樹に比べると剛性が無いので、強度を確保するために、こういう風に要所要所に「通しほぞ」を使用します。
針葉樹は柔らかくて広葉樹に比べると剛性が無いので、強度を確保するために、こういう風に要所要所に「通しほぞ」を使用します。
 聞くと、「すごく気に入っていて。毎日使っています。ウチはソファやベンチなどを置いてなくて、食事の時はもちろん、くつろぎの時間もいつもこの椅子に座って過ごしています。もう他の椅子は考えられないぐらい、座りやすいです…」とのことでした。
聞くと、「すごく気に入っていて。毎日使っています。ウチはソファやベンチなどを置いてなくて、食事の時はもちろん、くつろぎの時間もいつもこの椅子に座って過ごしています。もう他の椅子は考えられないぐらい、座りやすいです…」とのことでした。そういう状態で毎日使われて17年間…あっぱれです。色合いもいい感じに濃くなって、艶も出ており、作った当時よりもいい感じになっています。しかし、それにしても大事に使ってくださっているようで、大きな傷は見られません。ありがたいことです。
 現在は「栃一枚板こたつ座卓」のリメイクに取り掛かっています。このこたつ座卓も9年ほど前に制作し、千葉県まで納品(千葉県野田市S.N様)させていただいたものです。
現在は「栃一枚板こたつ座卓」のリメイクに取り掛かっています。このこたつ座卓も9年ほど前に制作し、千葉県まで納品(千葉県野田市S.N様)させていただいたものです。家族の生活スタイルも変わり「もう少し小さくしたい」とのご希望で、少し長さを小さくして作り直すことになりました。
さて、話は変わります。相変わらず猛暑の毎日が続いています。工房の中は(エアコンが無いので)常に35度ぐらいの暑さで、扇風機を回しても熱風しか来ません。特に午後1時以降、夜7時ぐらいまではその暑さがひきません。ときどき外に出ると、「ああ、涼しい!」と声が出るほどです。外の方が涼しいのです。
ですので、今年も夏場は朝早くから(7時前ぐらいから)仕事を始め、午後1時ごろまで続けます。そして、昼は食事と休憩タイムで4時ごろまで休みます。その後、また数時間仕事をするということにしています。

 しかし、そんな暑いのにこの前は孫を連れて、じぃじとばぁばで初めてのお出かけをしてきました。名古屋の東山動物園です。
しかし、そんな暑いのにこの前は孫を連れて、じぃじとばぁばで初めてのお出かけをしてきました。名古屋の東山動物園です。
孫はかわいいです。
ですので、今年も夏場は朝早くから(7時前ぐらいから)仕事を始め、午後1時ごろまで続けます。そして、昼は食事と休憩タイムで4時ごろまで休みます。その後、また数時間仕事をするということにしています。

 しかし、そんな暑いのにこの前は孫を連れて、じぃじとばぁばで初めてのお出かけをしてきました。名古屋の東山動物園です。
しかし、そんな暑いのにこの前は孫を連れて、じぃじとばぁばで初めてのお出かけをしてきました。名古屋の東山動物園です。孫はかわいいです。
でも、「ピザ会」だからピザを焼かないわけにはいきません。その担当は私です。ピザ窯のそばは灼熱地獄の暑さです。猛暑の中、ピザを4枚焼きました。(この役の跡継ぎを作りたいとずっと思っていますが、今のところやってくれそうな人はいません…。)
毎回ですが、皆さん本当にいい人たちばかりで、とても楽しい時間でした。(ソムリエ担当の友人の作るお酒は、毎回おいしすぎてついつい飲みすぎてしまいます。(笑))
「久しぶり」
2025.08.18
本当に久しぶりの更新になってしまった、この里山だよりです。(Instagramの方は随時更新しています。よかったら見てください。)
前回の更新から2か月以上たっていますが、その間にもいろいろなことがありました。ですので、その中でいくつかだけを書きます。
 まずは、何といっても「セルフビルドのアトリエ」が完成したことです。
まずは、何といっても「セルフビルドのアトリエ」が完成したことです。
前回の更新から2か月以上たっていますが、その間にもいろいろなことがありました。ですので、その中でいくつかだけを書きます。
 まずは、何といっても「セルフビルドのアトリエ」が完成したことです。
まずは、何といっても「セルフビルドのアトリエ」が完成したことです。
 セルフビルドでアトリエを建設しようと思い立ってから、約2年になりますが、実際に始めたのは昨年の秋からです。
セルフビルドでアトリエを建設しようと思い立ってから、約2年になりますが、実際に始めたのは昨年の秋からです。まずは昨年の11月。先行して庭の造成を始めました。12月ようやく材料となる木材が届いたので、刻み加工を始めました。12月末上棟、外壁貼り、その後3月下旬までは家具の仕事を進めたので、ほぼ中断。4月〜6月造作、外構などと進めてきました。

 始める前はこれほど本格的に家を建てることになるとは思っていませんでした。もちろん本格的な木造在来工法で建てるという事は決めていましたが、床や壁などは(経費を抑える理由で)在庫の材料をあり合わせで使っていこうと考えていました。
始める前はこれほど本格的に家を建てることになるとは思っていませんでした。もちろん本格的な木造在来工法で建てるという事は決めていましたが、床や壁などは(経費を抑える理由で)在庫の材料をあり合わせで使っていこうと考えていました。しかし、進むにつれて自分でも想像以上に良い家になりそうになっていったので、「どうせなら…」と本格的な材料と作り方で建てることにしていきました。

 基礎(息子の家を建ててくれた基礎屋さんにやっていただきました。立派なべた基礎です。)と電気工事、屋根貼りだけは業者にやってもらいましたし、上棟の日1日だけは大工さん数名を頼んで手伝ってもらいましたが、それ以外はすべて(大工仕事も、左官仕事も、外構工事も何もかも)自分一人で作りました。
基礎(息子の家を建ててくれた基礎屋さんにやっていただきました。立派なべた基礎です。)と電気工事、屋根貼りだけは業者にやってもらいましたし、上棟の日1日だけは大工さん数名を頼んで手伝ってもらいましたが、それ以外はすべて(大工仕事も、左官仕事も、外構工事も何もかも)自分一人で作りました。正真正銘のセルフビルドです。我ながら「よく作ったなあ」と感心しています。

 これからこの場所でお客様に休んでもらったり、ワークショップを行ったり、友人・知人を招いて食事会をしたり、もちろん家族で楽しんだりしていきたいと思います。
これからこの場所でお客様に休んでもらったり、ワークショップを行ったり、友人・知人を招いて食事会をしたり、もちろん家族で楽しんだりしていきたいと思います。すでに妻が友人を招いて何やらワークショップを行っていました。
「庭を眺める小さな家〜アトリエ〜 セルフビルドの記録5 造作編その3」
2025.06.04
かねてから建設中だったセルフビルドのアトリエも、だいぶん完成に近づいてきました。前々回の里山だより「庭を眺める小さな家〜アトリエ〜 セルフビルドの記録4 造作編その2」に続き、第3回目をご報告します。
 そもそも素人なので、家の建築については知らないことばかりでした。アルミサッシをネットで買ったのはいいですが、はたしてどうやってはめ込んだらいいのかなど、1からのスタートでした。
そもそも素人なので、家の建築については知らないことばかりでした。アルミサッシをネットで買ったのはいいですが、はたしてどうやってはめ込んだらいいのかなど、1からのスタートでした。
サッシ周りの枠(周りに回す板)でさえどうやってつけてあるのかがわからず、大工さんに聞くといい金具を紹介してくれました。こんなものがあるということも初めて知りました
 そもそも素人なので、家の建築については知らないことばかりでした。アルミサッシをネットで買ったのはいいですが、はたしてどうやってはめ込んだらいいのかなど、1からのスタートでした。
そもそも素人なので、家の建築については知らないことばかりでした。アルミサッシをネットで買ったのはいいですが、はたしてどうやってはめ込んだらいいのかなど、1からのスタートでした。サッシ周りの枠(周りに回す板)でさえどうやってつけてあるのかがわからず、大工さんに聞くといい金具を紹介してくれました。こんなものがあるということも初めて知りました
そして、その上にプラスターボードを貼り付けていきます。今回は壁には漆喰を塗ることにしたので、プラスターボードを貼ることにしたのです。
一部タイルを貼ることにしましたので、その施工をしました。タイルは30分ほど離れた街で、タイル生産の有名な笠原町というところへ行って買ってきました。その街には「モザイクタイルミュージアム」という施設があります。そこへ見学に行って参考にしました。

 接着剤を塗って、壁に貼り付けて乾くのを待ちます。
接着剤を塗って、壁に貼り付けて乾くのを待ちます。

 接着剤を塗って、壁に貼り付けて乾くのを待ちます。
接着剤を塗って、壁に貼り付けて乾くのを待ちます。

 細かいところもあってなかなか難しいです。それに、あまりきれいに塗るんじゃ面白くないのであえてむらむらに塗るのですが、それがなかなか難しいものでした。
細かいところもあってなかなか難しいです。それに、あまりきれいに塗るんじゃ面白くないのであえてむらむらに塗るのですが、それがなかなか難しいものでした。それでも何とか塗り終えて、いい感じに塗れたと自画自賛。
 そして次は電気工事になりますが、こればかりは電気屋さんにお願いします。しかし、「地下に埋めるから佐藤さん溝を掘って管を埋めておいて」と言われたので、土方作業もやりました。20メートルほど溝を掘りました。
そして次は電気工事になりますが、こればかりは電気屋さんにお願いします。しかし、「地下に埋めるから佐藤さん溝を掘って管を埋めておいて」と言われたので、土方作業もやりました。20メートルほど溝を掘りました。

 電気屋さんを待つ間に、基礎のコンクリートに仕上げ塗りをしました。シーラーを塗って仕上げのモルタルを塗っていきます。これも鏝作業です。
電気屋さんを待つ間に、基礎のコンクリートに仕上げ塗りをしました。シーラーを塗って仕上げのモルタルを塗っていきます。これも鏝作業です。なかなか難しかったです。左官屋さんはすごいなということを再確認できました。
まだ完全に完成ではありません。玄関のアプローチやらなにやら、やるべきことは残っています。それでも一応形にはなりました。とりあえずここで一旦完成と言えるほどになりました。

 昨年の11月末に材木の刻み作業を始め、12月末に上棟をし、その後3月の中旬ぐらいまでは家具制作に追われて建設は中断していましたが、4月5月と造作を進めて、やっとここまで出来ました。
昨年の11月末に材木の刻み作業を始め、12月末に上棟をし、その後3月の中旬ぐらいまでは家具制作に追われて建設は中断していましたが、4月5月と造作を進めて、やっとここまで出来ました。
満足感。自分で自分を「よく頑張った」とほめてやりたいです。
もちろん家の内外ともにもう少し作業は続きますが、本当に完成の暁には何らかの形で皆さんにお披露目出来たらなと思っています。

 昨年の11月末に材木の刻み作業を始め、12月末に上棟をし、その後3月の中旬ぐらいまでは家具制作に追われて建設は中断していましたが、4月5月と造作を進めて、やっとここまで出来ました。
昨年の11月末に材木の刻み作業を始め、12月末に上棟をし、その後3月の中旬ぐらいまでは家具制作に追われて建設は中断していましたが、4月5月と造作を進めて、やっとここまで出来ました。満足感。自分で自分を「よく頑張った」とほめてやりたいです。
もちろん家の内外ともにもう少し作業は続きますが、本当に完成の暁には何らかの形で皆さんにお披露目出来たらなと思っています。
 さて話は変わります…前回の里山だよりから1ヶ月以上たってしまいましたが、その間に庭の花たちは次から次へとまさに饗宴を繰り広げてくれました。
さて話は変わります…前回の里山だよりから1ヶ月以上たってしまいましたが、その間に庭の花たちは次から次へとまさに饗宴を繰り広げてくれました。モッコウバラが満開の4月末ごろ。シャクヤクやラナンキュラスも美しく咲いていました。
本当に今年はバラが美しく咲いてくれました。グラハムトーマス、パレード、バフビューティー、フィリスバイド、レオナルド・ダ・ビンチ、レディオブシャーロット、ジュビリーセレブレーションなどなど、我が庭にある10数種類のバラが今年は元気にたくさんの花を咲かせてくれました。
話は変わりますが、今年もゴールデンウィークの頃に、畑へ夏野菜の植え付けをしました。少し広くなった畑にたくさんの野菜を植えました。
「いろいろ」
2025.04.24
 さてそんな中、追われている仕事も何とかやっていました。千葉県のお客様のダイニングセットです。
さてそんな中、追われている仕事も何とかやっていました。千葉県のお客様のダイニングセットです。まずは椅子3脚分が完成し、塗装をしました。KOSI-KAKE2脚とπチェアフラット肘型(特注サイズ)です。

 端折って書いてしまいましたが、この椅子はなかなか難易度の高い椅子で、それなりに緊張しながら制作してきました。
端折って書いてしまいましたが、この椅子はなかなか難易度の高い椅子で、それなりに緊張しながら制作してきました。脚や背柱、肘柱などすべてが3次元的に角度がついていて、その角度も微妙に違います。少し間違えると組み立てることができません。
また丸棒もただ木工旋盤で加工するだけでなく、その後で鉋でもう一度削っています。そういう手間もかかっています。
そうこうしながら、何とか無事組み立ても出来ました。塗装をして完成です。
 かくして無事制作も終わり、先日千葉県船橋市まで納品に行ってきました。
かくして無事制作も終わり、先日千葉県船橋市まで納品に行ってきました。今回は「胡桃(クルミ)の円卓」「KOSI-KAKE 2脚」「πチェアフラット肘型 1脚」「SBチェア 1脚」「ホールベンチ」「栃(トチ)無垢一枚板 円座卓」となかなかの数のご注文でした。
ハイエースにパズルのように詰め込んで無事納品が出来ました。
このお客様は7年前に一度「πチェア」の価格をお問い合わせいただいたのですが、一度っきりで終わり、それから何の音沙汰もありませんでした。しかし、昨年の秋に突然「新居が完成したのでダイニングセットを作ってほしいです。一度工房へ伺ってご相談したいです」とメールをいただき、工房においでになりました。
結果的に上記のようなご注文をいただいたのですが、7年前に一度メールを頂いてから「実はずっとホームページは見ていました」とおっしゃいました。このお客様の中では半布里工房はずっと続いていたのだなとうれしくもあり、感謝もしました。
結果的に上記のようなご注文をいただいたのですが、7年前に一度メールを頂いてから「実はずっとホームページは見ていました」とおっしゃいました。このお客様の中では半布里工房はずっと続いていたのだなとうれしくもあり、感謝もしました。
そして、このお客様の納品が終わると、続いて同じ千葉県の野田市まで足を延ばし、違うお客様のお宅へ行きました。
以前制作させていただいた「こたつ座卓」をリメイクして、少し小さくしてほしいとのこと…久しぶりに(8年ぶりに)見ましたが、驚くほどきれいに使っていただいており、とてもうれしく思いました。
むしろ経年変化でさらに色合いが深まって、いい板になっていました。少し短くしたいとのこと…惜しい気もしますが、生活スタイルの変化もあるでしょうから、それはやむおえません。
そんな千葉県の納品行から帰ると、千葉県市原市のお客様のちゃぶ台の制作を続けました。例によって「天秤指し」の加工です。
以前制作させていただいた「こたつ座卓」をリメイクして、少し小さくしてほしいとのこと…久しぶりに(8年ぶりに)見ましたが、驚くほどきれいに使っていただいており、とてもうれしく思いました。
むしろ経年変化でさらに色合いが深まって、いい板になっていました。少し短くしたいとのこと…惜しい気もしますが、生活スタイルの変化もあるでしょうから、それはやむおえません。
そんな千葉県の納品行から帰ると、千葉県市原市のお客様のちゃぶ台の制作を続けました。例によって「天秤指し」の加工です。
こうして仕事の方も忙しい(今もまた次の仕事に取り掛かっています)ので、アトリエの建築の方はなかなか進んでいませんが、それなりに時間を見つけて進めています。それについてはまた次回に書こうと思います。
アトリエの前に新しく作った庭もだんだん形になってきています。
百聞は一見に如かず、久しぶりに庭めぐり動画を撮りましたので見てください。
もうすぐゴールデンウィークです。この時期は畑仕事が忙しい時期でもあります。そっちもやらなければと焦っている今日この頃です。
「庭を眺める小さな家〜アトリエ〜 セルフビルドの記録4 造作編その2」
2025.03.11
気がつけば3月になっています。毎年3月は何かと忙しい…仕事はもちろん、なぜか3月はいろいろ忙しいです。
ほかにも(私の場合は)、まずはアトリエの建築がありますし、温かくなって動き出した庭の手入れ仕事、そして畑もいよいよジャガイモの植え付けをしたり、草引きもしなければなりませんし、おまけに農業関係の会計の仕事があったり、神社関係では春の祭礼…。
その上もうすぐ孫がもう一人生まれそうで、そうなるとじじばばもじっとしてられません。一役を担うことになります。そんなわけで、今私は「超」「超」忙しく、毎日いろんなことに追われて生きています。
ほかにも(私の場合は)、まずはアトリエの建築がありますし、温かくなって動き出した庭の手入れ仕事、そして畑もいよいよジャガイモの植え付けをしたり、草引きもしなければなりませんし、おまけに農業関係の会計の仕事があったり、神社関係では春の祭礼…。
その上もうすぐ孫がもう一人生まれそうで、そうなるとじじばばもじっとしてられません。一役を担うことになります。そんなわけで、今私は「超」「超」忙しく、毎日いろんなことに追われて生きています。
さて話は変わり、「アトリエ建設」のこと…前々回に引き続き、「造作編その2」となります。

 内部の壁全体に断熱材を入れていきます。「グラスウール」を使用します。
内部の壁全体に断熱材を入れていきます。「グラスウール」を使用します。
簡単に入れているように見えるかもしれませんが、これがなかなか大変…隙間が出ないようにぴったりはめるのは結構難しいものです。

 内部の壁全体に断熱材を入れていきます。「グラスウール」を使用します。
内部の壁全体に断熱材を入れていきます。「グラスウール」を使用します。簡単に入れているように見えるかもしれませんが、これがなかなか大変…隙間が出ないようにぴったりはめるのは結構難しいものです。
ここまで書いてくると、順調に進んでいるように思われるかもしれませんが、実はそうではありません。本業の仕事の方も忙しく、アトリエの建設の方は結構止まったままで、なかなか遅々として進まずというところです。
とはいえ、足場屋さんに足場を返さなければならなかったり、電気工事屋さんの仕事の都合もあったり、完了検査も待っていたりします。いつまでも窓や入口のドアを作らずに放っておくわけにもいきません。雨風が吹き込んでしまいますので…。
つまり、そうぼやぼやしてはいられないのです。「出来るときにゆっくり作って行けばいいや」っていうわけにもいかないです。冒頭に書きましたように、3月は何かと忙しく…本当に大変です。ジレンマ…。
 そんな中、とりあえず入口のドアは作りました。建具の制作はどちらかといえば本業に近いので、なんとかなります。
そんな中、とりあえず入口のドアは作りました。建具の制作はどちらかといえば本業に近いので、なんとかなります。
とはいえ、足場屋さんに足場を返さなければならなかったり、電気工事屋さんの仕事の都合もあったり、完了検査も待っていたりします。いつまでも窓や入口のドアを作らずに放っておくわけにもいきません。雨風が吹き込んでしまいますので…。
つまり、そうぼやぼやしてはいられないのです。「出来るときにゆっくり作って行けばいいや」っていうわけにもいかないです。冒頭に書きましたように、3月は何かと忙しく…本当に大変です。ジレンマ…。
 そんな中、とりあえず入口のドアは作りました。建具の制作はどちらかといえば本業に近いので、なんとかなります。
そんな中、とりあえず入口のドアは作りました。建具の制作はどちらかといえば本業に近いので、なんとかなります。
しかし、まだまだやらなければならないことがたくさんあります。大仕事の内部の壁作りが待っています。また仕事の合間をみて、なんとか進めていこうと思います。
完成はいつ?外構は別として、なんとか4月初めに家本体を完成、完了検査…と目論んでいるのですが…無理かな?
そして、その後外構(入口のポーチなど)を進めて、ゴールデンウィークごろには何とか全完成と行きたいものです。それもあくまでも希望的観測です。ひょっとすると夏ぐらいになってしまうかもね。
…次回「造作編その3」へ続く。
完成はいつ?外構は別として、なんとか4月初めに家本体を完成、完了検査…と目論んでいるのですが…無理かな?
そして、その後外構(入口のポーチなど)を進めて、ゴールデンウィークごろには何とか全完成と行きたいものです。それもあくまでも希望的観測です。ひょっとすると夏ぐらいになってしまうかもね。
…次回「造作編その3」へ続く。
「木工体験」
2025.03.03

 最後は記念写真。「また来ます」「(お客様同士で)次も一緒にお願いしますね。今度はカッティングボードにしますか?」などと楽しそうに話して帰られました。
最後は記念写真。「また来ます」「(お客様同士で)次も一緒にお願いしますね。今度はカッティングボードにしますか?」などと楽しそうに話して帰られました。私が「楽しんでいただけましたか?」と聞くと「すごく楽しかったです!」との感想。
 あとからLINEで感想が届きました。「佐藤さんが褒め上手だということを記載するのを忘れていました」と追伸もありました。
あとからLINEで感想が届きました。「佐藤さんが褒め上手だということを記載するのを忘れていました」と追伸もありました。次回はいつになるか…希望がありましたら、いつでもご連絡ください。詳しくはこちらをご覧ください。
さて、工房では現在千葉県のお客様のダイニングセットの制作中です。πチェアフラット肘型の制作も佳境に入っています。
後脚の成形です。南京鉋という鉋で削って形を整えていきます。
後脚の成形です。南京鉋という鉋で削って形を整えていきます。
さて、肘の成形加工に移ります。大まかに切り出した肘部材を削って、きれいな形に仕上げていきます。
その様子も動画でどうぞ。
その様子も動画でどうぞ。
「庭を眺める小さな家〜アトリエ〜 セルフビルドの記録3 造作編その1」
2025.02.27

 座面に座繰り加工をします。「四方反り台鉋」という鉋を使って掘っていきます。
座面に座繰り加工をします。「四方反り台鉋」という鉋を使って掘っていきます。(このあたりの作業の様子は動画でも取ってInstagramでも上げています。主にInstagramのストーリーズで現在の進行中の様子を上げています。日常的な様子はInstagramの方で更新することが多いです。良かったらInstagramを見て、できればフォローもしてください。)
「庭を眺める小さな家〜アトリエ〜 セルフビルドの記録2 上棟編」
2025.02.14
工房では船橋市のお客様のダイニングセットの制作中です。テーブルの脚先の加工です。機械や手仕事を駆使して脚先の飾りを作っていきます。

 続けて、今度は旦那さんのご注文である「πチェア フラット肘型」の制作に入ります。今回は旦那様、奥様、子どもたちそれぞれに違う椅子をご注文いただきました。
続けて、今度は旦那さんのご注文である「πチェア フラット肘型」の制作に入ります。今回は旦那様、奥様、子どもたちそれぞれに違う椅子をご注文いただきました。まずはπチェアからです。座板の接ぎ合わせです。
さて、前回に引き続き「庭を眺める小さな家〜アトリエ〜 セルフビルドの記録」…今回はいよいよ「上棟」編です。
「(昨年の)年内には必ず上棟するぞ!」と決めて刻み作業をしていたのはいいですが、「材料の木材がなかなか入ってこなかったこと(11月下旬にようやく運び込まれました)」「私一人で刻み作業をしていたこと」「予想以上に”本格的な”刻み作業だったこと(指導の宮大工の棟梁の要求レベルが本格的なものだった?)」などなどで、予想以上に大変な仕事でした。(もう少し簡単かと思ってました。甘かった!)
棟の日はもう決まっているし、「間に合うか?」と焦りながらの作業が続きましたが、何とか予定通りに準備を進め、上棟の日を迎えました。さすがに上棟は私一人ではできませんので、宮大工の棟梁に頼んだり、私の知り合いの大工さんに頼んだりして応援に来てもらいました。
「(昨年の)年内には必ず上棟するぞ!」と決めて刻み作業をしていたのはいいですが、「材料の木材がなかなか入ってこなかったこと(11月下旬にようやく運び込まれました)」「私一人で刻み作業をしていたこと」「予想以上に”本格的な”刻み作業だったこと(指導の宮大工の棟梁の要求レベルが本格的なものだった?)」などなどで、予想以上に大変な仕事でした。(もう少し簡単かと思ってました。甘かった!)
棟の日はもう決まっているし、「間に合うか?」と焦りながらの作業が続きましたが、何とか予定通りに準備を進め、上棟の日を迎えました。さすがに上棟は私一人ではできませんので、宮大工の棟梁に頼んだり、私の知り合いの大工さんに頼んだりして応援に来てもらいました。
実は私が一番心配していたのは、高い屋根の上に登って屋根(垂木や板)を貼っていく作業でした。それだけはちょっと怖くて、当初は棟梁に「佐藤さんもちゃんと上ってやるんやぞ。当たり前やろ(笑)」などと言われていましたが、やはり怖い…。
ところが当日は他の大工さん二人が手際よくやってくれて、私はひたすら材料を上げることに徹していることができました。良かった(ホッ…)。
ところが当日は他の大工さん二人が手際よくやってくれて、私はひたすら材料を上げることに徹していることができました。良かった(ホッ…)。
先にも書きましたが、この家、小さな小屋の割には(宮大工の棟梁の指導のお陰で)結構本格的な木造在来工法の家で随所になかなかの仕口が見られます。
「庭を眺める小さな家〜アトリエ〜 セルフビルドの記録1」
2025.02.04
 そして、天板の裏に「寄せ蟻」の加工をします。まずはルーターで蟻桟を掘っていきます。
そして、天板の裏に「寄せ蟻」の加工をします。まずはルーターで蟻桟を掘っていきます。
さて、話は変わりますが、前回の里山だよりから2ヶ月、私は大工さんに変身していました。我が”jagar's garden”の一角に「庭を眺める小さな家」(今のところ正式名称は決まっていませんが、通称「アトリエ」と呼んでいます)をセルフビルドしています。
とにかく自分で作ることが好きな私は、今までにいろんなものを作ってきました。工房のハーフビルド、木製カヌー、車庫、庭の東屋、小屋、床の間などなど…いろいろ作ってきましたが、最後はやはり「家」を作ってみたいという気持ちはありました。
実は、この計画はもう2年ほど前から考えており、当初は完全にどこかの工務店に頼もうかと考えたり、あるいは大工さんの手を借りて建前までお任せし、その後ハーフビルドをしようという計画も考えたりしたのですが、いずれも予算的なことを考えて断念したのです。結局、家を建てるという計画はいったん諦めました。それが1年半ほど前のことです。
ところが、その後いろんな人に「どうしてやめたのですか?!」とか「絶対やるべきですよ!」とか、挙句の果てには「私が材料や機械など世話をしてあげるから、佐藤さんやりましょう。佐藤さんなら建てれますよ!」「木材の支給は応援しますよ」などと多くの方から背中を押される形になりました。何か事が進むときというのは、こういう風にいろんな力で後押しされるものですね。
結局ハーフビルドでもなく、完全にセルフビルドで建設をすることにしたのです。
とにかく自分で作ることが好きな私は、今までにいろんなものを作ってきました。工房のハーフビルド、木製カヌー、車庫、庭の東屋、小屋、床の間などなど…いろいろ作ってきましたが、最後はやはり「家」を作ってみたいという気持ちはありました。
実は、この計画はもう2年ほど前から考えており、当初は完全にどこかの工務店に頼もうかと考えたり、あるいは大工さんの手を借りて建前までお任せし、その後ハーフビルドをしようという計画も考えたりしたのですが、いずれも予算的なことを考えて断念したのです。結局、家を建てるという計画はいったん諦めました。それが1年半ほど前のことです。
ところが、その後いろんな人に「どうしてやめたのですか?!」とか「絶対やるべきですよ!」とか、挙句の果てには「私が材料や機械など世話をしてあげるから、佐藤さんやりましょう。佐藤さんなら建てれますよ!」「木材の支給は応援しますよ」などと多くの方から背中を押される形になりました。何か事が進むときというのは、こういう風にいろんな力で後押しされるものですね。
結局ハーフビルドでもなく、完全にセルフビルドで建設をすることにしたのです。
「根太レス」という工法ですので、大引きを落とし込む欠き取り加工もします。
土台の組み立てをしました。
こうしてまずは土台が完成しましたが、その後はまた刻み作業が続きました。昨年の年内に上棟まで済ませたかったので時間にも追われ、結構必死で作業を進めました。

 とにかく、何といっても木材が重いので大変です。
とにかく、何といっても木材が重いので大変です。
重い木材、たとえば110mm×270mm×3メートル超、あるいは110mm×150mm×4メートル超なんていう大きな柱をあちらへこちらへと運びながら刻みを進めることを一人でやるのは大変なことでした。

 とにかく、何といっても木材が重いので大変です。
とにかく、何といっても木材が重いので大変です。重い木材、たとえば110mm×270mm×3メートル超、あるいは110mm×150mm×4メートル超なんていう大きな柱をあちらへこちらへと運びながら刻みを進めることを一人でやるのは大変なことでした。
こうして、刻み作業を一人で延々と進めていきました。難しくてわからないことばかりでしたが、その都度宮大工の棟梁や知り合いの大工さんに聞いて、教えてもらいながらなんとか進めていくことができました。
そしていよいよ12月22日、建前(上棟)の日を迎えることになりました。…次回に続く!
そしていよいよ12月22日、建前(上棟)の日を迎えることになりました。…次回に続く!